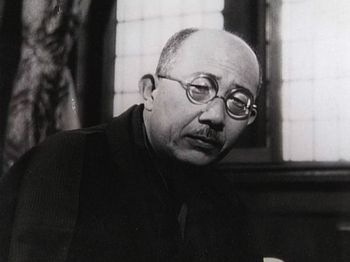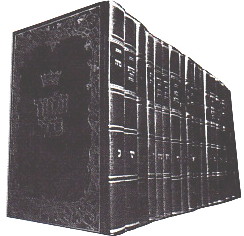5年目をスタートするにあたり
少し、自分の今までの経営のあり方を
振り返ってみた。
信賞必罰
ということのあり方について
考えつづけてきた4年間でもあった。
称されるべき行為・結果に対しては
賞として報いる。
組織としての 原理原則 が
犯されたときには躊躇なく罰する。
これらが保たれなくなったときに
組織は間違いなく崩壊する。
しかし・・・
わかってはいるが
これが、なかなか出来ないものなのです。
特に小さい組織の場合は
様々な意味において
社員バランスが保ちにくいことが
一番の要因かと思う。
賞することは良いが、罰は難しい。
近年、 モチベーション や 社内風土カイゼン など
ということが経営の中の流行言葉のように使われるが
わたしは少々、 違和感 を感じる。
それらは誰かや、組織から与えられるべきものなのか?
気を配られるべきものなのか?
それらは、個々の意志で産み出され、
育むべきもの ではないのか?
こう感じながら、まだまだ未熟な経営に
自分なりの経営観を貫くべく、5年目を目指すことにします。